ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。
素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。
どうでもいい は じ め に
今回は,うんと趣向を変えて,小説風,物語風のような文章を並べてみた。どれもこれも,ちょっと青臭く,ありきたりのシチュエーションで,申し訳ない。もっと,真剣に書けば,少しはサマになるかもしれないが,そこまで完成させるスペースも才能もない。できるだけ,いろんなパターンにしたつもりだが,かなり無理があった。
なお,言うまでもないが,どれもこれも,「妄想」 の産物であると断っておこう。
それぞれのアルバムについては,今回は,別ファイルに一括して記載した。ここ をクリックすると別窓か別タブで開くと思うが,ブラウザによっては,そうはならないかもしれない。その時は,ゴメンナサイ。また,各アルバムのジャケットをクリックすると当該データへ飛ぶようにした。この場合,リンク先の 「データ編」 のジャケットをクリックすると,このページの同じアルバムに戻るようにしている。

は つ こ い
あれは,小学校の一年生の事だ。
教室の黒板のそば,教壇を下りた辺りで,僕はその子と向き合っていた。オルガンが傍にあった。スポット・ライトが当たっているかのように,その場所のことは,はっきりと覚えているのに,教室に他の誰かいたのかどうかは,まったく覚えていない。それに,どういう脈絡でそういうことになったのかも記憶にない。
向き合った女の子が言う。
「あんた痩せてるね・・・。私の手より細いんじゃない?」
そう言ってその子は,僕の手首に細く白い親指と中指を回した。彼女の手のぬくもりが感じられた。
「ほら,こんなに隙間ができる・・・」
確かに,彼女の指で作った環と僕の手首の間に隙間ができ,彼女はもう一方の手の人差し指をその隙間に入れてみせた。
「きみだって細いじゃない」
今度は,僕がその子の白い手首に指を回した。同じように,隙間ができる。
「ほら,いっしょだよ」
「ほんと・・・」
たったそれだけの出来事だった。
それからほどなくして,その子は,別の学校へ転校して行った。名前も覚えていない。だが,あの時が,僕が女の子を意識した,最初の瞬間だったことは間違いない。
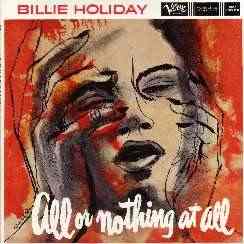
右 か 左 か
彼を心底から愛しているのに,パパはわかってくれない。とってもハンサムな彼だけど,この前,仕事に失敗してしまったから怒ってるんだわ。
それにしても,なんだって,彼と抱き合ってるところをアイツに見られてしまったのだろう。ずっと,ばれないように気をつけていたのに。アイツは,パパの言うことなら何だってその通りにするから,パパは,アイツを私と結婚させようとしていた。アイツはアイツで,露骨に私に言い寄ってくるような下司野郎なんだから。
そう私のパパは,この辺りじゃ誰もが一目置くボス。アイツは,そのナンバー・ツーと言うわけ。で,私の彼はというと,この間の仕事で大きな失敗をしてしまって,すっかり信用をなくしてしまったばかりだったから,私が慰めてあげていたんだ。そしたら,そんなところをアイツに見られてしまって,パパにコクられてしまった。
パパは,大きな平手で私を殴っておいて,「あんな奴は殺してやる」,と,部下に命じて彼を捕まえてしまった。パパは,一度言い出したら必ず実行する。そしたら,どこかの海にコンクリートの重しをつけて,彼は沈められてしまう。誰も気がつかないように。
「パパ,お願い。パパの言うとおりにするわ。それに,パパは心の広い人でしょ。せめて,殺すのだけは止めて,追い出すだけにして・・・」
彼が生きてさえいれば,まだチャンスはあるかもしれないから,私は必死でお願いしたんだ。そうしたら・・・
「そうだな・・・お前がそう言うのなら,奴にも生き残るチャンスをやろうか。」
「お願い,そうしてあげて・・・」
「ただし,生き残るチャンスは,2分の1だ。地下室に2つの扉があるだろう。そのドアを開けるのが奴の試練の場だ」
自分の思い付きがとっても気に入ったのか,パパは楽しそうに,ちょっと凄みのある笑顔でそう言った。そんな笑顔を向けられた部下たちなら,きっと竦みあがってしまうに違いない。
「どういうこと?」
「片方の扉を開けたら,女が入っている。お前もよく知ってるあの女だ。いい女だぜ。ちょいと阿婆擦れだがな。奴を彼女と結婚させてやる。そうして一生,ワシが飼い殺しにしてやるよ。お前は,ワシの決めた男と結婚するんだ。もう一方のドアを開けようとしたら,その途端,一巻の終わり。ドア・ノブに高圧電流が流れているというわけだ。どうだ,面白いだろう。お前にも,皆にも,見物させてやろう。ワシの言うことを聞かなかったらどうなるか,誰にでもわかるだろうからな」
その日が来る前に,私は,電流の細工をした男から,どちらのドアに細工したかをなんとか聞きだした。
そしてついにその日が来た。地下室に連れて来られた彼に,
「さあ,お前の運命の日だ。好きな方の扉を開けるがいい。運が良ければ死ななくて済むぜ」
パパは,笑いながらそう言い渡した。彼は,パパのそばに隠れるようにして立っていた私に目を向けた。右か左か・・・どちらのドアが危険なのか,私が知っていることを彼は悟っているんだ。それくらい,私たちの心は通じ合っているんだもん。
でも,私は,一瞬,迷ってしまった。彼が私以外の女と結婚して生き続けるのを黙って見続けていられるのか,それとも,いっそ私の指示通り死んでしまった彼のことを密かに思い続ける方がいいのか・・・
「さあ,早く開けろ!」 パパは,怒鳴った。
私は,パパにも他の誰にも気づかれないように,右側のドアを目で示した。彼は,ゆっくりと右側のドアに向かって歩き出した。
(これは,Frank Richard Stockton という作家の 『女か虎か (The Lady, or the Tiger?)』 (1884) という短編の下手な焼き直しですので,あしからず)
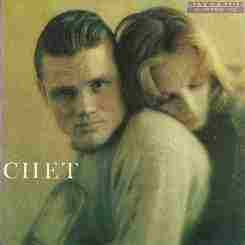
事 件
男の死体が発見されたのは,あるマンションの十階の一室で,もう半年も前のことだ。そのマンションは,とりたてて高級というわけではないが,建物の入口は,インターホンで住人を呼び,玄関ロックを部屋から開錠してもらうか,6 桁の暗証番号を入力して開錠しないと入れない建物だった。
死体の発見者は,男の恋人だった。会う約束をしていたので来たのだが,インターホンで呼び出しても返事がなかったので,シャワーでも浴びてるのかと思い,教えてもらっていた暗証番号でマンションの玄関を開錠し,男の部屋に向かった。そして,合鍵を使って室内に入ると,上がり框で頭から血を流して倒れている男を見つけ,呼びかけたり,身体を揺さぶったりしたあと,携帯電話で救急車を呼んだという。そして,救急隊から警察に連絡された。そう女は言った。
死因は,おそらく,金槌のような鈍器で後頭部を殴られたもの。凶器は,発見されなかった。
室内には,男の指紋と発見者の女の指紋は,多数残っていたが,それ以外の指紋は特定できなかった。
第一発見者の女は,もちろん厳しく取り調べられたが,死亡推定時刻は彼女が訪れる 1 時間前で,マンションの玄関にある防犯カメラには,それより前の時間帯に彼女の姿は映ってはいなかった。それに,カメラの映像からは,他にも,特に怪しい人物は誰一人見出せなかった。
男の身辺調査は念入りに行われたが,男を恨んでいる人物は見つからず,また何らトラブルも見出せなかった。女の身辺調査も行われたが,これと言って不審なことはなく,その半年ほど前に,偶然,あるバーで隣同士になり知り合ったもので,その時,男は仕事仲間と 2 人連れで,女も女子大時代の友人と 2 人で来ていたという。それまでに,その 4 人が会ったことはなかったと,それぞれの連れが別個に証言している。
* * *
「うまくいったわね」,と,背中に身体を寄せて女が言う。「あなたと彼は,同じマンションに住んでるだけで,知り合いでも何でもなかったんだから,ね」
確かに,うまくいった。アイツは,オレが同じマンションの 3 階の住人だとは知りもしなかったろう。
あの日,オレは,毎日着ている仕事着を来て,手袋をすると,女が用意したウィスキーの入った箱を手に,あいつの部屋のインターホンを鳴らした。
「お届け物です」
すぐに応答したアイツは,ちょっと不審がってはいた。「どうやって中へ入ったんだ?」
「はい,他の部屋にも,お届け物がありましたので,そちらのお宅から先にお届けしたもので・・・」
「そうか・・・」
ガチャリと鍵が開き,アイツが顔を覗かせた。
「これなんですが・・・印鑑かサイン,お願いします」 オレは,肩でドアを支えながら言った。
「ペンはあるか? 忘れたって? ちょっと待ってくれ。それじゃあ,印鑑を取ってくるから・・・」 と,アイツが背中を見せた瞬間,オレは隠し持っていた金槌でアイツの後頭部を力いっぱい殴りつけた。アイツは,音をたてて倒れた,思わず廊下の左右を見回したが,誰にも見られてはいなかった。もう死ぬのは間違いないと思ったが,オレは,血の海を踏まないように気をつけながら,少しだけ中に入り,しばらく様子を窺っていた。返り血が玄関の壁を染めていたし,床にもどんどんあふれていった。殴った時,持っていた箱で顔を隠すようにしたおかげか,案外,オレ自身には,かからなかったようだ。
もう一度,廊下の様子を確かめ,オレはドアを閉めた。女から預かっていた合鍵で施錠すると,エレベーターではなく,階段を使って自分の部屋に戻った。もちろん,血のついた箱も持ち帰ってきた。女からは,成功しても失敗しても連絡はするな,と言われていた。通話記録を残さないための用心だろう。オレは,服を脱ぎ,洗濯機に放り込むと,シャワーを浴びることにした。
数日後から,知らない名前の手紙が届いた。その封書には,現金が入っていた。そんな手紙が,毎日のように届くようになった。差出人の名前も違えば,消印を見ると,場所も違っているようだった。時には,お菓子の箱の中に,半分になったお菓子といっしょに入っている小包もあった。金額もマチマチだったが,頼まれた時に渡された半額と合わせると,確かに,最後には,約束どおりになった。
が,今になって思うと,これじゃ,安すぎる。人殺しの相場なんて知りはしないが,しかし,女の居所も知らなければ,聞いている名前だって,本当かどうか怪しいものだ。少なくとも,あれから半年,何ごともないのだから,諦めるしかないのかもしれない。
そんなことを思いながら,その日,オレは晩飯を兼ねてよく行く居酒屋へ行った。以前より,懐も暖かいので,酒を飲みながら飯を食っていた。
「ここ空いてます?」 と女の声がした。頷いて見ると,例の女だった。
「はじめまして・・・」 何食わぬ顔でそういうと,すぐに注文し始めた。「知らないふりしてて・・・」 と小声で言う。
それからは,食べながら,何気ない風に,まるで初対面のように,ポツリポツリと話し合いながら,2 時間近く,酒を飲んでいた。
「ねえ,せっかくお知り合いになれたんだから,もう一軒,どこか行かない?」
店を出ると,女はすぐにタクシーを停め,いっしょに乗るように言った。小綺麗なバーに行くと,そこで 小一時間過ごし,再び,タクシーに乗り,ターミナル駅まで行く。そこで降りると駅の中をぐるりと回り,別の出口からまたタクシーを拾った。そして・・・このホテルまで来たのだった。
部屋に入ると,オレに凭れ掛かるようにして,「本当に,よくやってくれたわ」
「だけど,少なすぎやしないか・・・」 オレは日頃思っていたことを口に出した。
「そうねぇ・・・」 女は,オレがそう言い出すことを予期していたようだった。「でも,時間はたっぷりあるわ。もっと,あなたのことを知らなくちゃ・・・」
「オレがよく行く店まで知ってるくせに・・・オレのことは,ずいぶん調べてあるんだろう。だけど,どうしてアイツを・・・あんたら,どんな関係だったんだ?」
「あなたは,そんなこと,知らない方がいいの。・・・今夜は,ゆっくり楽しみましょうよ」
* * *
最初から睨んでいたことが正しかったのだとわかった。同じマンションに住んでいるあの宅配会社に務めている男だとは気がつかなかったが,女の方が,きっと誰かと接触すると,張り付いていたのはムダではなかったのだ。動機もはっきりしないが,ふたりの関係と,確たる証拠を見つけることができれば・・・まだまだ時間がかかるかもしれない。だが,あいつらが犯人であることは間違ってはいない筈だ。それに,おそらく実行犯の男も,消されるに違いない。その時が,勝負だ。そう私は,確信している。

小 径
「素敵な道ね・・・」
木漏れ日のさす静かな道を歩きながら,彼女は,彼に寄り添った。一足ごとに,周囲の木々から舞い落ちた枯れ葉がさくさくという音をたてた。
「そうだろう。僕の好きな道なんだ・・・」
彼は,そう言ってしまってから,これまで何度か歩いたこの道に,彼女を誘わなければ良かった,と今さらながらに考えるのだった。これまで,彼女とは,できるだけ初めての場所を訪れるようにしていたのだ。それなのに,つい,ここへ来てしまったことを後悔し始めていた。
あれから何年になるだろう・・・封印していた記憶を彼は辿った。あの池の畔のベンチに腰掛け,長い時間を過ごした日々。そのベンチには,彼が愛した女性 (ひと) がいつも座っていたものだった。そのベンチからは,ある有名な作家が宿泊したという老舗ホテルの屋根が見えた。
(一度,あのホテルに泊まってみたいものだね。だけど一泊どれくらいするんだろう,高いんだろうなぁ)
それからふたりは,立ち上がると,この小径へ向かった。
(痴漢が出るって噂もあるけど・・・)
それくらい林の中の小径は,昼間でも薄暗くひっそりとしていた。その時も,ふたりの前後には誰も歩いていないようだった・・・。
「これからどこへ行くの?」
その声に彼は現実に引き戻された。どこへ? あの女性 (ひと) はそんなこと訊かなかったな。それくらい,いつもいっしょに歩いていたんだ。それなのに,どうしてか,別れてしまったんだ・・・やはり,この道のことは,封印しよう。素敵な小径の名前もあるが,その名前もいっしょに・・・
「何か食べに行こうか」
これから先,いっしょに暮らしていくことになっている彼女と歩を進めていった。
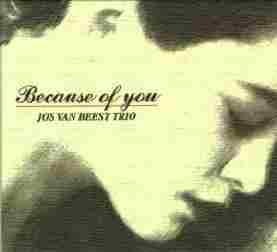
日 常
洗濯機を回し,掃除をする。掃除が終わった頃には,洗濯機も止まり,ベランダに洗濯物を干す。彼のシャツのシワを伸ばしながらハンガーにかけ,下着を吊るす・・・
そんな毎日が,少し気恥ずかしくも,嬉しかった時期もあった。食卓に向かい合って食事をしながら,何気ない一日を語り合うことも,楽しい時間だった。たまの休日に彼といっしょに買い物に出かけると,隣の奥さんに,「いつも仲がいいわね」,と冷やかされたのも,満更ではなかった。彼の柔らかく,優しい手の感触を思い出し,ふっと頬が熱くなることもあった。
そうして毎日が過ぎていった。当たり前のように,同じ日々が繰り返される。喧嘩することもなく,大きな問題もなく,一日一日が流れていく。
どれくらい年月が過ぎたのだろう。いつから,あんな日々を懐かしく,遠い昔のことのように思うようになったのだろう。日常が大きく変わったわけではなく,あの頃と同じように過ごしているのに,不満があるわけでもないのに,あの夢を見ているような時間だけが戻って来なくなったのは・・・
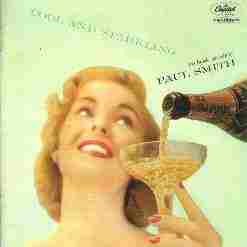
愛 の デ ィ ナ ー
「食事の前に,乾杯しようか。それにしても,今日は一段と綺麗だね。もう食べてしまいたいぐらいだ」
「また,そんな・・・それじゃ,食べてごらんになる?」
「いいのかい?」
「それくらい,愛してくれなくちゃ」
「もちろん,愛しているよ」
「私も,あなたを愛してるわ」
「嬉しいよ・・・それじゃ,今夜の料理について,ちょっと,シェフと相談してくるよ」
「今日は,どんなご馳走なのかしら・・・」
「じゃあ,ちょっと待ってて・・・」
「ねぇ,きみ・・・シェフがきみと相談したいんだって。なにか,スペシャルなサプライズを考えてるらしい」
「なにかしら・・・シェフは,厨房ね。行ってみるわ」
「旦那さま,お食事の用意が整いました」
「おお,血のしたたるようなステーキだな,美味そうだ」
「そりゃ,もちろんでございます。旦那さまへの愛情がたっぷり入っておりますから。こちらのお飲み物も,ぜひどうぞ。まだ,新鮮,絞りたてでございます」
「おお,この赤い色の美しいことと言ったら・・・」
彼は,笑顔を浮かべながら,一人での食事を始めた。
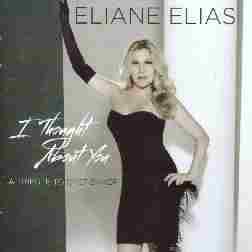
何 処 へ
今年の春,例年通り,数名の新たな社員が入ってきた。僕の課にも,一人の女の子が配属された。その年入社した新人のほとんどが大学を出たばかりだったが,彼女だけは,3 年ばかり別の会社に勤めていたこともあったので,年齢も少し上だったが,やはり仕事経験があるせいで,すぐになじみ,半年も経った頃には,何年も前からいっしょにやってきたような感じさえするほどだった。何かにつけてよく気がつき,しかも頭の回転が速いというのか,僕たちの課が進めていたプロジェクトにも,いなくてはならないほどになっていた。
そのプロジェクトがまとまり,N 県 A 市にある X という会社へプレゼンに行くことになった。その担当に,僕と彼女が選ばれたのだ。
プレゼンはうまくいき,契約も決まった。正式な契約は後日ということになったが,なにはともあれ,目的を果たした僕たちは,とりあえず祝杯をあげることにした。はじめは,帰りの新幹線の車中で缶ビールと名物の駅弁でと考えていたが,予定より早く終わったので,どうせなら,新幹線の時間に間に合うように名物料理を食べてから帰ろうということにした。十分に時間はあったのだから。
駅前にあった料理屋に入り,注文していると,そこへ,さっきまで相手をしていた X 社の社員たちが入ってきたものだ。結局,いっしょに飲もうということになり・・・誘われるままに,ちょっと飲み過ぎた僕たちは,とうとう電車の時間を逃してしまうことになってしまった。
「悪いことしちゃったなぁ・・・近くに安いビジネス・ホテルがあるから,案内しますよ」
X 社の社員が,近くのビジネス・ホテルを紹介してくれた。運よくシングル・ルームが 2 部屋空いていて,僕たちは,鍵を受け取るとエレベーターに乗り込んだ。
「ちょっと,飲み過ぎたみたい・・・」
エレベーターの中で,彼女は,ちょっとフラフラしながら言った。部屋のある階に止まった時,その少しの振動で,バランスを崩した彼女を,僕は支えなければならなかった。彼女の髪の香りが鼻腔をくすぐった。
「先輩・・・酔い覚ましに,お水でも飲んでいきません」
すっかり僕に支えられながら,彼女は,足を運ぶ。512 号室のドアを開けると,急に,彼女は,僕の胸の中に顔を埋めた。
「わかってるんです・・・先輩に,奥さんがいることも・・・でも,私・・・」
僕は彼女の肩を持って引き離そうとした。だが,なぜか,僕は,彼女にキスしてしまった・・・そして,そのまま狭いシングルベッドで,越えてはならなかった一線を越えてしまった。
その後も,ふたりの関係が続いたというわけではなく,あの一夜だけのことだった。社内では,それまでと何も変わらなかった。しかし,その年の終わりに,彼女は突然,辞表を出し,会社を辞めてしまった。
そうして,3 年が過ぎた。彼女のその後が気にならないではなかったが,どこにいるのか,何をしているのか,消息は誰も知らず,探す手立てもなかった。その間に,僕は,父親になった。
そんなある日,子どもを連れ,妻と 3 人で買い物に出かけた時,ふと通りかかったコンビニの前で掃除をしている女性と目が合った。それが,彼女だった。一瞬,身体中に電気が走ったように感じた。彼女も凍りついたように動きを止めた。
「あなた,どうしたの?」
妻の声に,僕は,我に帰り,先に歩き出していた妻の後を追った。一度,振り返ると,彼女は,立ち尽くしたままだった。
次の日,僕は,妻には内緒で有給休暇を取り,そのコンビニへ出かけた。彼女はいた。どうでもいいような買い物をし,レジに立つ彼女と仕事の後で会うことを約束した。ためらっていた彼女も,不承不承,短時間なら・・・と応じてくれた。
仕事の終わる時間に,僕は,店の前まで彼女を迎えに行った。近くの喫茶店に入ると,3 年間のこと,今,どうしているのか,どこに住んでいるのか,いろいろ訊きだした。その日は,それだけのことだったが,それから,定期的に会うようになった。ただ,会うだけで,話をするだけで良かった。僕は,どこかに置き忘れていたときめきを感じていたのだ。彼女も,避けるわけではなく,会い続けてくれた。
そして,彼女の誕生日・・・僕は,彼女の住んでいるアパートでお祝いをしようと提案し,彼女も,喜んでくれた。僕は,その夜,花屋で一輪のバラを買い,ちょっとしたプレゼントを持って,彼女のアパートへ向かった。
すると・・・そのアパートの入口に,妻が立っていた。
「あなた,何処へ行くつもりなの?」

前 夜
「この曲,覚えているかい」
「さあ,聴いたことがあるような気がするけど・・・」
「これは,母さんが好きだった曲だよ。母さんと初めて出逢った時に弾いていた曲なんだよ。ラウンジでこの曲を弾いたら,母さんが来て,さっきの曲,大好きなんだって言いに来たんだ。それが,最初」
「へぇ・・・知らなかった。そんな話,してくれたことなかったわ」
「お前が生まれて,寝かしつける時に,よく口ずさんでいたよ」
「ぜんぜん,覚えてないわ・・・母さんが歌うのなんて聞いたことないもの」
「母さんが死んだ後・・・お前が学校へ行っている間に,毎日,この曲を弾いていたよ。だけど,いつまでもそうもしてられないから,もう二度と弾かないことに決めたんだ」
「じゃあ,今日は,どうして?」
「今日は特別な日だから・・・明日,お前が嫁いでいくこと,この曲に乗せて,母さんと一緒にお祝いするためだよ。必ず,幸せになるんだよ」
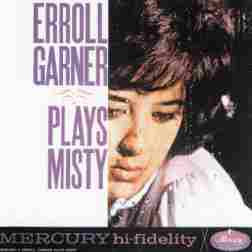
霧 の 中
その男が入ってきたのは,雨でも降りそうな曇天の午後,まだ店を開ける前だった。
「まだ準備中だよ」
私は声をかけたが,一癖ありそうな男は構わずにカウンターまで来ると一枚の写真を取り出した。
「この男,知らないか」
仕込中の手はそのままに,チラッと写真に目を向けた。私の知っている彼とよく似ていると思ったが,手は止めなかった。
「このあたりにいるらしいんだが,ここへ来たことはないかい」
「知らないねぇ・・・この人,誰なの? それより,そんなこと訊くあんた,いったい何なのさ」
「ああ,悪かった。先に出さなきゃいかんかった・・・」 男はそういうと,草臥れた背広の内ポケットから黒い手帳のようなものを出すと,「M 警察の者なんだ。この写真の男に,本当に見覚えないか」
「知らないわねぇ・・・この人,何したの」
男は写真を指で叩きながら,
「あんた覚えてないかい,そうだなぁ,もう 3 年も前のことだからなぁ。M 市の居酒屋の店主が金貸しを殺した事件。その居酒屋の店主だよ。オレ達が駆けつけた時には,コイツ逃げたあとだった。それから,ずーっと追いかけてるんだよ」
「あんまり悪そうな人に見えないけど・・・」
「さあてな。ま,いろいろ事情があって,コイツが逆上したのもわからんわけじゃないが,殺したのはマズイよな,いくらなんでも」
「事情って?」
「殺された金貸しというヤツ,前から目をつけてたワルなんだ。言葉巧みに相手を騙して,金を貸しておいて,あとから大きな利子をつけて,返せ,とやる・・・返せなきゃ,店を取り上げて店主を追い出すようなヤツだったんだ。ま,言い方悪いが,騙される方も騙される方だけどね。それにしても,そんな目にあった被害者の中には,自殺したり,無理心中した人も少なくなかった。で,コイツもコロっと騙された挙句,店を取り上げられ,悲観した奥さんが生まれたばかりの子どもを抱いて,近くのビルから飛び降りたんだ。その翌日に,コイツは,金貸しの店に行き,持っていた包丁で一刺し。ついでに止めようとした別の男も刺して,逃げていったというわけだ」
男の目は,喋りながらも,店中に向けられていた。
「そんな悪いヤツを殺したのに・・・」
「ま,逃げなきゃ,情状酌量ってこともあったかもしれんが,3 年も逃げてちゃなぁ。それに,金貸しは,即死。もう一人の男も,三日後に死んじゃったからな。いくらなんでも無罪ってわけにゃいかんよ。それに,オレ達も最初は,どこかで自殺するんじゃないかって思ってたんだが・・・そんな気配はないし,その後,あちこちの県で見かけられているんだ。」
「そう・・・で,この辺にいるって?」 私は,何気なく訊いてみた。
「去年の年末までは,隣りの N 県にいたことがわかったが,行ってみるともう逃げたあとだった。駅で聞いたところでは,ヤツに似た男がこっち方面の電車のホームにいたというし,それに,ヤツの奥さんと子どもが死んで,ちょうど 3 年目。そう,3 年前の今日だったかな。この町には,奥さんの親戚の建てた墓もあるしな・・・おっと,喋りすぎたようだ。もし,コイツを見かけたら連絡してくれよな。名刺を置いてくよ・・・そこに階段があるけど,ここ,2 階もあるのかい」
「あるわよ。物置にしてるだけだけど・・・どうして? 見たいの?」
「いや・・・,2 階に宴会場でもあれば,宴会に使えるかと思ってな。また,来るよ。今度は,客として」
去年の年末,ひどい霧の出た夜遅く,常連客も帰り,そろそろ店を閉めようかと思っていた時に,彼が入ってきた。地味な帽子を目深に被り,夜も遅いのにサングラスをかけていた。「すみません,一本だけ飲ませてもらえませんか」
「もう火を落としちゃったし,店を閉めようと思ってんだけど・・・」
彼は,頷くと肩を落として,出て行こうとした。「いいわ,飲ましてあげるわ。そのかわり,暖簾を入れといてくれる。熱燗でいいわね」
まだ冷め切っていなかった湯を沸かしなおすと,お酒に燗をつけながら,残り物の煮物の小鉢をカウンターに置いた。「私も飲んじゃおうかしら・・・」
「どうも,すみません」
「あんた,見かけない人ねぇ・・・」
「前に,M 市に住んでたことがあるんです。そう・・・3 年ほど前になりますか・・・」
ぼそぼそとそれだけ言うと,黙々と酒を飲んだ。帽子を脱ぎ,サングラスも外したが,ずっと,顔を伏せるようにし,私の顔をほとんど見ようともしなかったが,お銚子が空になると,「お勘定してください」 と,初めて顔を上げて言った。
「いいわよ,奢ってあげる。私も飲んでるんだから・・・もう一本どう,遠慮なんかしないで・・・私の愚痴でも聞いてよ」
恐縮しながら,彼は,座りなおした。そうしてまた顔を伏せながら,それでも,私の話を静かに聞いてくれたものだ。夫が念願のこの店を開き,なんとか子どもと三人,食べていけるようになった矢先に,夫はガンであっけなく死んでしまった。なんとか,私一人で,この店を切り回している時,子どもが肺炎にかかり,病院に連れて行くのが遅くなって死んでしまった,という話をした時だけ,彼の目頭が涙で光ったのを私は見逃さなかった。
「あんた,何してるの?」
「いえ,別に・・・ただ,命日じゃないけど,墓参りだけしようと思って,戻ってきてしまったんです」
その夜,ふたりで 7,8 本も飲んだだろうか。もっとだったかもしれない。泊まるところを決めていないという彼を,無理やり 2 階の物置代わりの部屋に泊めた。昔,遅くなった時には,夫ともそうしたもので,押入れには布団を入れたままにしてあった。私も安アパートには戻らなかった。だけど,布団を並べて寝たというだけだった。
それから,今日までの半年近く,彼は,2 階にいた。食堂でアルバイトしたことがあるから,と仕込みを手伝ってくれていたが,彼の包丁を扱う腕は,とてもアルバイトで覚えたといったものではなかった。できたら,店の手伝いをして欲しいと頼んだが,もしかしたら,知り合いに会うかもしれない,顔を見られたくないんです,と店を開けている時間は,2 階で一人ひっそりと過ごしていたものだ。昼間も,ほとんど,外出することはなかった。
それが今朝になって,ちょっと出かけてきます・・・と珍しく外出した。あの最初の夜のように,帽子を目深に被り,サングラスをして・・・
夜になって,店を開ける時間になっても,彼は帰って来なかった。昼間来た刑事の話を思い出すと,きっと墓参りに行って,二度とここには戻って来ないだろうと思った。
「こんばんは・・・一本つけてよ」 常連の不動産屋のオヤジが電気屋の店主といっしょに,大声で入ってきたのは,もう店を閉めようかと思った頃だった。今夜も,珍しくじめじめとした深い霧だった。「なんか外も鬱陶しいけど,女将も景気悪い顔してるねぇ・・・って,こっちも景気悪いからなぁ,ハハハ」
「それより,知ってるかい。昔,ほら 3 年ほど前に M 市で悪徳金融業者が殺された事件・・・今日,あの犯人が捕まったんだってさ」
私は,小鉢を持つ手が震えるのを止めることはできなかった。その時,また店に客が入ってきた。
帽子を目深に被り,サングラスをかけた男・・・。不動産屋のオヤジたちから離れてカウンターに座ると,「すみません,一本だけ飲ませてもらえませんか」
やっぱり,手の震えは止まらなかった。ふっと涙と笑みが同時にあふれてきた。「今夜も,熱燗でいいわね・・・」

裸 足 に な っ て
昨日,僕は,彼女に宛てて一通の手紙を出した。とても,直接は言えなかった。何度も書き直し,書き直しては,破ってしまったりしたほどだったが,やっとのことで書き上げて封をした。そうして,出勤する時,駅前のポストに投函した。コトンと落ちる音がして,僕は,一瞬,出さない方が良かったか,取り戻す方法はあるだろうか,と考えた。だけど,そんな方法は思いつかないし,間もなく来る電車に乗らなくてはならない。
社に着いて席に座ると,すぐに,彼女は,いつも通りお茶を出してくれた。いつもなら,「ありがとう,でも,お茶くらい自分で入れるから,気にしてくれなくていいのに・・・」,と言い,「いいんです,私,お茶入れるの好きなんですから」,と彼女が笑顔で答えるようなやりとりをしていたが,今朝の僕の心臓は,ドキドキと激しく打っていて,もしかしたら,彼女に聞こえてしまうのではないかと心配するほどだった。だから,やっと,「ありがとう」,としか声が出なかった。
おそらく手紙は,早ければ明日届く筈だ。そして,明日の土曜日の午後,彼女が家に帰ると手紙が着いているだろう。その明日は,僕は,朝から出張なので,ここには来ない。だから,今日一日,僕は,できるだけ何気なくしていなければいけないんだが,耐えられるだろうか。
手紙には,明後日の日曜日に,もし良ければ,いっしょに N 高原へ行かないか,と書いた。彼女の家の最寄り駅からの電車の時刻を調べ,それに乗って来てくれれば,僕は,N 高原駅で待っている,それからバスに乗って,と・・・だけど,もし,郵便が遅れれば,どうしようもない。いや,明日配達されたとしても,彼女がどう思うか。別の予定があって来れないのなら仕方がないが,予定がなくても,来ないかもしれない,それが最悪の結果だ。
日曜日の朝,僕は,寝不足のまま,出かけた。子ども頃の遠足の前日のような落ち着かない夜に,十分眠ることができなかった。ただ,大きく違うのは,遠足なら晴さえすれば必ず行けるが,今日は,行ってみなければ,どうなるかわからない。来てくれないのではないか,そんな悪い予感だけが,打ち消しても打ち消しても湧き上がってくるのだ。
N 高原駅までは,およそ 2 時間の行程だった。彼女には,一本遅い電車を伝えてあるので,30 分あまり,僕は,駅で待つことになる。期待と不安が交互に襲ってくる時間は,それが永遠に続くのじゃないか,と思えるほどだった。
そして・・・列車が来た。出口から数人の客が出てきたが,彼女はいなかった・・・と,少し間を置いて,彼女がいつものスカートと事務服とは違う,スポーティーな服装で現れたのだ。
「お待ちになりました? それより,バスの時間がもうすぐじゃないですか,急ぎましょう」
何も言う間もなく,さっさとバス停に向かう彼女を追いかけることになってしまった。確かに,僕たちが乗り込むとすぐにドアが閉まり,さっき降りてきた数人の客と僕たちだけを乗せたバスは発車した。
「だって,少し電車が遅れてたんです。間に合って良かった・・・」 屈託なく彼女はそういうと,膝に置いたリュックを見せて,「お弁当,作ってきました」
すっかり,僕は,嬉しい,良かった,という気持ちを噛みしめる余裕もなく,彼女のペースに巻き込まれていた。バスの窓から差し込む明るい日の光を,眩しそうに浴びる彼女の笑顔がイキイキと輝いているのを,僕は,凝視めるだけだった。
バスから降りると,しばらく登り坂の道をゆっくりと歩いた。「前から,一度,来てみたかったんです。でも,一人じゃ,なかなかチャンスがなくて・・・」
1 時間ばかり歩くと,N 山の麓の草原に着いた。そこは,N 山に連なる起伏のある草原で,所々に,湧き出る地下水をたたえた池や,秋には一面のススキが金色に輝く場所もあった。が,登山口に通じる道と N 山の一つの稜線まで広がる雑木林との間は,背の低い草に覆われた斜面になっていて,その斜面からは,太古には火山だったという N 山の切り立った屏風のような崖の一部やススキの群生する少し低くなっている平地や池を同時に眺めることができた。
バスに乗っていた他の客たちは,N 山に登るために,さらに進んでいったが,僕は,その斜面の草原の方に彼女を連れて行った。そこは,僕のお気にいりの場所であった。都会の雑踏を忘れることのできる風景・・・時々,都会生活に息苦しくなると来てみる場所だった。もちろん,少年時代のように,山に登れればそれに越したことはないのだが,今の僕は,病気のために,登山はできない。
そう,その病気のために,僕は,息苦しくなるほど彼女のことを想っていること伝えきれないでいた。だから,今回は,ただ,彼女と数時間でもいいからいっしょにいたいという願いを賭けたのだ。彼女が来てくれ,お弁当まで作ってくれ,いっしょに食べ,少々,ぎごちないながらも,お喋りする時間が持てたことで,僕は,満足だった。
僕は,草の上に横になり,広がる青い空を眺めていた。すると,彼女は,靴を脱ぎ捨て,裸足になると,僕のすぐ横に腰を下ろした。「あなたも靴を脱いだら・・・締め付けられなくて,とっても,気持ちいいわよ」
両手をついて,空を見上げた彼女は,大きく息を吸い,吐き出した。事務所で見かける彼女とは違って,本当に,自由でイキイキとした様子だった。
「誘ってもらって嬉しかった」 と,彼女は言った。「ずっと,あなたのことが気になっていたんです。でも,あなたは,きっと病気のこと気にしてるんだと思ってた。ええ,私,事務をしてるんだから,あなたの病気のことなんかずっと前から知っていたわ。あなたの書類を見ればわかるもの。そんなことは,どうでもいい。ずっと,こんな日を待ってた。これからも,ずっと続いて欲しいと思ってるし・・・」
僕は,思わず,彼女の手を握り締めた。できるだけ,生き続けていたいと思った。

し お り
最初は,小学校の 5 年生の秋だった。
その頃,僕たちの学校では,授業が終わると,各自の椅子を机の上に載せ,教室の後ろの方へ引っ張っていったものだ。そうして,その後,掃除当番が教室を掃き,机を戻し,椅子を下ろし,雑巾で机を拭いていく。ゴミは,運動場の隅にあった焼却炉まで運んでいく。
その日,僕たちは掃除当番だった。机の間を掃いていると,彼女がそばに来て,僕に手紙を手渡した・・・それは,ラヴ・レターだった。
小学校時代は,僕と彼女は,同じ友達仲間と,毎日のように下校時間まで学校の中で遊びまわっていた。
中学生になると,ふたりの家の間にある道路が境になっていたので,別の中学に通うことになった。それでも,土曜日になると,午後にはふたりで公園で会ったりしていたものだ。本当に,土曜日が待ち遠しかった。
そうして高校生になる。同じ高校に通うことになり,しかも,1 年生の時には,同じクラスになったものだ。
そう・・・授業が終わったあと,校舎の陰で抱き合い,初めてキスをしたのもその頃だった・・・その日はそのあと,ずっと,心臓が激しく脈打ち続けていたほどだった。
ちょっと素敵な表紙のノートで交換日記をしたり,時には,喫茶店で長い時間おしゃべりをしたり・・・最初は,電車通学だったが,歩いていけない距離ではないことを知ると,朝,少し早めに家を出て待ち合わせ,毎日,学校まで歩いて通学したりした。
彼女が大学生になり,同じ大学に合格はしたが,僕は,迷った末に一年浪人することにした。そして,翌年,僕も大学生になった。
その間も,毎日のように会い続けていた。20 歳を過ぎ,もう離れたくない,ずっとこのままいっしょにいたい・・・そう思い続けていた。
だが,その一方で,僕は,彼女を縛りつけ,所有しようしているのではないか,と思うようになった。それは,もうかなり前から気づいていたのに,意識し,あるいは,無意識の裡に抑え続けていたのだ・・・と。それでいて,やはり,彼女と離れたくはないし,自分だけのものにしたいと思い,その間で揺れ動き,苛立つようになっていったのだった。
ある日,僕は,もう深く考えることもできず,発作的に,彼女と別れてしまった。
それから,何年経ったろう。その間には,彼女への想いを断ち切るために,彼女と交わした手紙などを燃やしたりもした。だけど,そんなことでは,彼女への想いを消すことはできないのはわかっていた。
それに,一枚のしおりが本の間に挟んだままになっている。押し花と色紙を細かくちぎって葉にした手作りの紫陽花のしおりだ。裏には,彼女の文字で,「七色花」 と書かれている。そのしおりを見るたびに,僕の記憶が,あの校舎の陰で,日が傾いて夕焼け色に染まるまで抱き合っていた頃に戻っていくのを止めようとはしないでいる。
どうでもいい あ と が き
今回は,いつもとずいぶん違う趣向にしたが,如何だったろう。いつも以上に,無駄な文章を読まされた,と思われた方がほとんどだと思っている。ま,単なる私の自己満足だと笑って許していただくしかない。
ただ,最初に,タイトルを思いついたのが,もう一昨年,2017 年のことで,その時は,いつも通りの雑文のつもりだった。
それが,ちょっと,違う方向に考えを変えたのが,昨年 (2018) のことで,はじめは,無理してでも全編でひとつの話にして,ジャケットは,挿絵感覚で・・・と思ったのだが,そうはうまい具合なジャケットがない。それに,それだけの物語を書く自信もなかった。
そこで,短い話で一枚と決め,実際に書き始めたのは,10 月からだった。物語というより,梗概程度,アイデアだけのメモでもいいや,と。
中には,先に書いたように,名作のひどい焼き直しがあったり,犯罪小説風なのに,たぶん血がついたであろう靴の跡だとか階段へのドアの取っ手に血がついたんじゃないかとか,なんか映画で見たことがあるような話があったりで,不十分だなぁ,とは自覚しているし,盗作になるんじゃないか,なんて心配になる。それでも,このシリーズのチェンジ・オヴ・ペースになればいいか,と恥を忍んでアップした次第です。
(2019. 1. 3.)