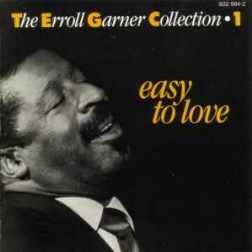
ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。
素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。
私がジャズを聴き始めたのは,もうかれこれ 40 年以上前の学生時代のこと。少しずつレコードを買い漁り,のめりこんでいったわけだが,その頃は,町の商店街の中にあったレコード店でもジャズのアルバムを買えたので,最初の頃に手に入れたアルバムは,すべて日本のレコード会社が発売したものだった。
大学生だった私がアルバイトをしていた書店の近くの商店街にあったレコード屋にも,もちろん,ジャズのレコードがあり,アルバイト代を手にその店に直行したこともあった。
その書店のあった最寄り駅は高架駅だったが,その駅下にもレコード店があり,その店では,2000 円以上のレコ-ドを買うとスタンプ・カードに 1 つスタンプを捺してくれ,スタンプを 10 個集めると 2500 円のレコードと交換できた。
当時,LP 1 枚は,1500 円,1800 円,2200 円,2300 円というものが主流だったが,最新盤は,2500 円だった。スタンプを集めるには,2000 円以上のアルバムなので,そういうのは駅の店,2000 円以下のものは,アルバイト先の近くの店で買っていたものだ。
学校のあった天王寺に近い阿倍野の大手の支店には,輸入盤も数多くあり,おそらくジャズ通の店員さんがいたんだろう,品揃えは,町のレコード屋とは比べものにならないほど充実していた。初めて輸入盤を買ったのもその店だったし,日本盤でも欲しいものはたいていそこにはあったものだ。
数年経って,私もそれなりにジャズを知るようになった頃,その阿倍野のレコード屋の品揃えが明らかに変わってしまった。輸入盤が減り,日本盤もどこにでもあるようなものが中心になったのだ。おそらく,ジャズを担当していた人が,本店の方に異動したのか,辞めてしまったのか・・・その推測は間違っていないと思っている。他の店でも,同じようなことを何度も経験しているし,そういう店に勤めていた人が,ジャズの専門店を始めることもあったからだ。
実のところ,最近,毎月行くお店の店主も,もともとは別のレコード店で働いていて,独立した人の一人なのだ。
こんな昔話をするつもりではなかった。
先に書いたように,レコードを集め始めた当初は,日本盤ばかりだった。中に入っている 「解説」 を読んで学ぶ,という意味合いもあったが,輸入盤に手を出したくても,近所のレコード店にはなかったのだから,どうしようもない。
そんなレコードの 「解説」 を読んでいると,曲目が邦題で記されていることも少なくなかった。最近の日本盤はどうなのか知らないが,昭和 40 年代から 50 年代にかけては,それが普通だったのだ。ただ,私は,できるだけ原題で覚えるように心がけていた。それは,『スイング・ジャーナル』 誌に時々掲載されていたミュージシャンのディスコグラフィーを見ると,そこには,英語のままでデータが記されていて,それを読む時に,《いつか王子様が》 と覚えていても,《Someday My Prince Will Come》 のことだとわからなければ,ずいぶん損な話だ。もちろん,《マイ・ファニー・ヴァレンタイン》 のように,単にカタカナにしたものが多いが,それでも,《My Funny Valentine》 という字面で覚えておく方が間違いがない。
「字面」 と書いたのは,元来,高校の時の英語の試験では欠点を取っていた私だから,「発音」 はどこまでもカタカナだ。発音を知らない単語の曲名などは,ローマ字読みで覚えてしまっていたので,カタカナで曲名を記されている 「解説」 を読んだ時に,一瞬,「?」 が頭の周りに飛ぶことがあって,英語のタイトルを見て,「あらら,これ,そう読むの!」 なんてことも少なくなかったものだ。
というわけで,今回は,スタンダードと 「邦題」 の関係について調べてみたいというのが,テーマだ。ほとんど,英語の直訳もあれば,誤訳もあったり,まったく,原題を思いつかないようなものもある。どこまで,できるか,とりあえず始めてみようか。
たとえば,《月光価千金》 という歌をご存知だろうか。私より上の世代の方なら,エノケンが歌っていたあの歌だな,とわかるかもしれない。あるいは,ナット・キング・コール (Nat King Cole) の歌としてかな。しかし,原題まで知っている方は少ないのではないかと思う。原題は,《Get Out and Get Under the Moon》 といい,Larry Shay 作曲,William Jerome,Charles Tobias 作詞の 1928 年の歌だ。残念ながら,この曲のジャズ・ヴァージョンは,私の手持ちアルバムにはなかった。
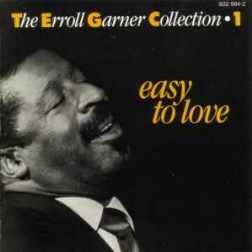
《私 の 青 空》
エノケンといえば,《私の青空》 という歌も有名だった (いやいや,エノケンなら 「渡○のジュースの素」の歌だろう,という声も聞こえてきそうだが・・・)。 堀内敬三の訳詞で,「狭いながらも 楽しい我が家・・・」 という一節が記憶に残る。原題は,《My Blue Heaven》 で,「青空」 だから,‘Blue Sky’ かと思ったらそうではない。‘heaven’ にも 「空」 という意味はあるから,ま,いいか。作詞は George Whiting,作曲は Walter Donaldson で,1927 年に出版されたもの。
手持ちのアルバムを探すと,左の Erroll Garner “Easy To Love” (EmArcy) に,Erroll Garner(p), Eddie Calhoun(b), Kelly Martin(ds) のトリオによる 1964 年 6 月 24 日録音のものがあった。
もともとは,Erroll Garner の未発表を集めたLPだったようだが,それがCDになったもの。だから,Erroll Garner のページにデータを示しておいたように,1961 年から 1964 年までの録音が収録されている。ジャケットでわかるように,‘Collection・1’ なんだが,コレしか持っていないのであしからず。
写真は,Veryl Oakland,デザインは Tom and Ellie Hughes。
実はこの曲,Red Garland も録音している。1962 年 10 月 9 日に,Red Garland(p), Wendell Marshall(b), Charles Persips(ds) のトリオで録音したもので,この日は,“When There Are Grey Skies” (Prestige) の時なのだが,この曲だけ長らくお蔵入りしていたもの。2001 年にボーナス・トラックとして加えられたが,はっきり言えば,加えなくてもよかったと思う。“When There Are Grey Skies” というアルバムのブルーなイメージには合わないハッピーな演奏だ。(出来そのものは,いつも通りの悪くないものなので,出てきたのは,私個人的には嬉しいが・・・)
ところで,「あお」 というと,まず,「青」 という漢字を思い出す。だが,これ以外にも,「あお」 と訓む漢字はある。
いつものように,まずは,『広辞苑』 で 「青」 をみる。
(古くは、目立たぬ色を表す語で、灰色をも含めていった) ①青色である。緑、藍、蒼、碧に通じていう。(以下略)
新村 出 編 『広辞苑 第五版』 (1998,岩波書店)
いわゆる,「青信号」 が緑色なのに,「青」 というのはどうしてか,ということで,古来,日本では,「緑」 のことも 「あお」 と言っていたということは,よく知られていると思うが,「灰色」 もかっては,「あお」 だったということだ。
「青」 という漢字の次に思い出すのは,「蒼」 ではないだろうか。「蒼穹」,「蒼茫」 といった語がある。「蒼穹」 は,まさに 「あおぞら」 のことだし,「蒼茫」 は,青い広がりといった感じだろうか。また,五木寛之が直木賞を受賞した作品は,『蒼ざめた馬を見よ』 という短編だった。
この 「蒼ざめた馬」 という言葉は,『新約聖書』 の 『ヨハネの黙示録』 の第 6 章第 8 節に出てくるがのだが,手持ちの 1987 年版の 『聖書 新共同訳』 (1987,1988,日本聖書協会) では,
そして見ていると、見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は 「死」 といい、これに陰府 (よみ) が従っていた。
とある。
『聖書』 は,これまでに何度も日本語訳されていて,最初は文語体だったものが口語体へと変わってきている。そうした,古い聖書について,まとめている 「Bible」 というサイトがあり,たまに参考にさせてもらっているが,そこで閲覧できる 『明治訳 「新約聖書」 (1904年版)』 の 「約翰默示録」 では,
われ觀しに一匹の灰色 (あをざめ) たる馬を觀たり之に乘れる者の 名は死という陰府 (よみ) その後に隨へり
とあり,先の 『広辞苑』 で書かれていたように,「灰色たる」 に 「あをざめたる」 というルビがふられている。1904 年というと,明治 37 年だ。その頃では,まだ,「灰色」 も 「あお」 として通じていたわけだ。
もうひとつの 「碧」 は,ふつう 「みどり」 とも訓むが,「碧玉」 といえば,今では,「ブルー・サファイア」 を指すし,「紺碧」 といえば,『広辞苑』 によれば,「やや黒みを帯びた青色」 と説明されているように,やはり,「あお」 を指すようだ。
一口に 「あお」 といってもなかなか奥深いものがある。
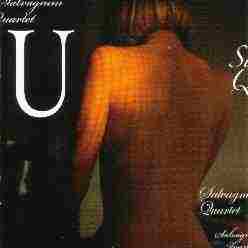
《あ な た は 恋 を 知 ら な い》
ほとんど直訳だけど,それなりに雰囲気が残る邦題としては,《あなたは恋を知らない》 はどうだろう。もちろん,《You Don't Know What Laove Is》 が原題。Don Raye 作詞,Gene DePaul 作曲の 1941 年の曲だ。
Sonny Rollins, John Coltrane の名演の他,1950 年代から現代に至るまで,数多くのミュージシャンが取り上げている。私の手持ちのアルバムで数えてみると,52 の演奏があり,数からいえば第 6 位になっている。(2019 年 4 月 1 日現在)
こうなると,どのアルバムで紹介するか,ひじょうに悩んでしまう。ありきたりじゃない方がいいか・・・というわけで選んだのが,2005 年 11 月 19 日に録音された,Massimo Salvagnini “U” (Velut Luna) で,Massimo Salvagnini(ts), Sandro Gibellini(g), Giorgio Panagin(b), Roberto Facchinetti(ds) のピアノレス・カルテットでの演奏。いわゆるスロー・バラードというより,少し速めで刺激的。
写真は,Massimo Salvagnini とあるが,カヴァーまでそうなのかどうかはわからない。中に入っているブックレットの写真は,どうやら本人が自撮りしたようだが,カヴァー写真はどうなんだろう?
今年の 3 月,BS で 『小さな恋のメロディ (Melody)』 という映画をやっていた。実は,この映画,昭和 46 (1971) 年に日本で公開された時,私は,映画館で見たものだ。さっそく,当時買ったパンフレットを本棚から抜き出してみた。50 年近く前のものだから,表紙などは,さすがに日に焼け,汚れてしまっていたが,中は,比較的キレイだった。それに,当時の半券 (学生 400 円だった) が挟んであり,ついでに,「46.7.15 北野劇場」 と日付と映画館の名前を万年筆で記録してあった。高校一年生の 1 学期の期末試験の終わったあとだろう。調べてみると木曜日だから,試験休み期間だな・・・誰と行ったか・・・それは,ヒミツです。
映画は,11 歳の少年と少女が 「結婚」 するというもの。「結婚」 と言っても,ただ,「ずっといっしょにいたい」 というお互いの気持ちを表したものだ。初めてそういう気持ちを抱いたふたり。そうした子どもたちを理解できない親や先生たち。それまで,ふたりを茶化して同級生たちが結束して,結婚式を行い,阻止しようとする大人たちからふたりを守ろうとする・・・そんな純粋な子どもたちの,初々しいというか,あまりにも穢れのない心持ち・・・その映画を見た私は,16 歳になる直前だったが,素直に共感したように思う。
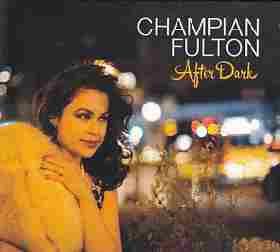
《縁 は 異 な も の》
原題を直訳したような邦題だと,すぐにわかるというものだが,邦題では,元のタイトルが何だったのかわかりにくいものもある。ここに挙げた 《縁は異なもの》 もそのひとつではないだろうか。これが,《What A Difference A Day Made》 のことだとすぐに結びつく人は素晴らしい。
Maria Grever と Stanley Adams の作詞で,作曲は Maria Grever,1934 年の曲だ。そんなによく取り上げられるわけではないが,まったくないわけではない。今回は,比較的新しいアルバムで,Champian Fulton “After Dark” (Get String Records) でいこう。Champian Fulton(p, vo), David Williams(b), Lewis Nash(ds) というトリオでの演奏。Champian Fulton のヴォーカルも楽しめる。全 11 曲中の 4 曲には,彼女の父親である Stephen Fulton のトランペットが加わる。録音は,2015 年 8 月 17 日。
写真は,Tayla Nebesky,デザインは,Ian Hendrickson-Smith。
「縁は異なもの」 とくれば,「味なもの」 と続ける。男女間の 「縁」 の不思議さというか,面白いものだという成句だ。
こういう七五調の成句は覚えやすい。このように,気の利いたことを七五調にするというのが,日本人にとって自然なことなのかもしれない。「万葉集」 の時代から和歌や俳句,都都逸など,その歴史はとても古いのだから,身体に染み付いているのだろう。
「旅は道づれ 世は情け」,「無理が通れば 道理引っ込む」 とか,「クシャミ三回 ○○三錠」,「ゴホンといえば 龍○○」,「すぐおいしい、すごくおいしい」 のようにCMで使われるキャッチ・フレーズも七五調であることが多いようだ。(最後のは,五七調か)
五七調,七五調の名文で思い出すのは,『曽根崎心中』 だ。冒頭の 「げにや安楽世界より・・・」 から,最後の 「・・・恋の 手本となりにけり」 まで見事という他ない。
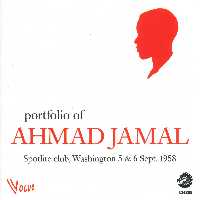
《時 さ え 忘 れ て》
Lorenz Hart と Richard Rodgers のコンビによる 1939 年の曲である 《I Didn't Know What Time It Was》 を 《時さえ忘れて》 と言われると,一瞬ピンと来ないのではないだろうか。その曲を Ahmad Jamal “Portfolio Of Ahmad Jamal” (Vogue) でいかがかな。Ahmad Jamal(p), Israel Crosby(b), Vernell Fournier(ds) というおなじみのトリオ時代の 1958 年 9 月 5, 6 日の ワシントン (Washington) は <Spotlite club> でのライブで,もともとは,Cadet が原盤。「間」 の Jamal の演奏だ。「間」 というより,ウォーキング・ベースとドラムスだけの時間がけっこうあって,ますます,なんじゃコレ,となるかもしれない。が,確かに,《I Didn't Know What Time It Was》 には違いない。
ジャケットについては,記載が何もなかった。
この歌が作られた頃というのは,それこそ,「大学は出たけれど・・・」 という就職もままならないような大不況の時代がようやく終わって落ち着いてきた頃のようだ。だけど,1929 年に始まった大恐慌の記憶は,まざまざと残っていて,そういう時代を歌った曲だ。「これまでの何がなんだかわからずに戸惑っていたけど,あなたに出会ったことで,やっとそんな時を忘れることが出来る・・・」,そんなニュアンスのようだ。
「恋は盲目」 なんて言葉があったが,なにかに打ち込むと,まったく時間のことや周囲のことを忘れてしまうことがある。好きな人といっしょにいると,時間を忘れてしまったようなこともあったもんだ。ホントに偶 (たま) にだが,最近では,こういった文章を書いている時に時間を忘れることがある。だからといって,書いたものが良かったか,といえば,そうでもないような気がするが・・・だけど,そういう無心になれる瞬間を持つことは,悪いことではない。そういう夢中になってしまうような瞬間を持ち続けたいものだ。

《魅 惑 さ れ て》
同じ Lorenz Hart と Richard Rodgers の 1940 年の作品 《Bewitched》 が 《魅惑されて》 ならば,なんとなくわかるか。
《Bewitched》 は,ジーン・ケリー (Gene Kelly) が唯一主演したブロードウェイ・ミュージカル 『パル・ジョーイ (Pal Joey)』 に使われた曲で,374 回上演されたという。ただ,この曲自体は,その時には,それほど評判を得たわけではなく,先にフランス語に訳されてフランスでヒットし,その後,アメリカに逆輸入するという形でスタンダード化したという。というのは,ミュージカルで使われた時には,現在とは違った歌詞だったらしく,それが,当時のアメリカの倫理観にそぐわない歌詞だったことで,アメリカではヒットしなかったらしい。ただ,どんな内容だったのかはよくわからない。
こういうことは,当時はよくあったようで,たとえば Cole Porter の曲など,たとえば 《Love For Sale》 なんていう曲は,アメリカでは放送禁止になった。「自由の国」 というアメリカだが,案外,倫理的に狭い潔癖な部分があったわけで,いつかどこかで書いたような気もするが,一般の女性が素足を見せることはタブーだったし,ハリウッド映画でも,長いキス・シーンは御法度だった時代もある。「禁酒法 (Prohibition)」 や 「赤狩り (Red Scare)」 といったことも,そういうアメリカだからこそだろうか。女性に対しても,「良妻賢母」 を求めていたのは,日本だけではない。「ウーマン・リブ (Women's Liberation)」 運動が起こったのもアメリカからだったわけだ。
ここに選んだアルバムは,Bill Anschell の “Shifting Standards” (Origin) というアルバムで,Bill Anschell(p), Jeff Johnson(b), D'Vonne Lewis(ds) のトリオでスタンダード 9 曲を演奏したもの。2017 年 11 月 19 日の録音。
このピアニスト,なかなか面白い処理をしてスタンダードを聴かせる。一筋縄ではいかない注目のピアニストのひとりだ。
カヴァー・デザインは John Bishop。
ところで,“Bewitched” というアメリカ製のテレビ・ドラマをご存知だろうか。昭和 40 年代に,日本でも放映され,人気のあったドラマだ。その時の日本でのタイトルは,『奥様は魔女』。
人間そのもののダーリン (Darrin) と結婚したのが,サマンサ (Samantha) という魔女。魔法は使わないという約束を交わしているが,なかなかそうも行かず,折に触れて,サマンサは魔法を使う。魔法を使う際,ピクピクッ,とサマンサが鼻を動かすのだが,普通の人には出来ないもので,それができるという特技のために,エリザベス・モンゴメリー (Elizabeth Montgomery) がサマンサ役を射止めたという。このヒットのおかげで,エリザベス・モンゴメリーといえばサマンサというイメージが出来てしまい,彼女自身は,後に,悩んだらしい。
現在,サマンサタバサというブランドがあるが,そのブランド名を耳にするたびに,『奥様は魔女』 を思い出してしまうのは,昭和世代のせいか。

《誰 も 奪 え ぬ こ の 思 い》
この日本語のタイトルは,Gershwin 兄弟の作った 1937 年の 《They Can't Take That Away From Me》 という曲。“Shall We Dance” というミュージカル映画のために作られたもので,フレッド・アステア (Fred Astaire) と ジンジャー・ロジャース (Ginger Rogers) が歌ったという。
上のような邦題になったのは,歌詞に,次のような一節があるからで,その箇所を例によって 『ジャズ詩大全』 から引用してみる。
きみが帽子をかぶるさまや
お茶をするしぐさとか
そういったことすべての思い出
そうそう、それだけは誰も僕から奪えやしない!
村尾陸男 著 『ジャズ詩大全 13』,1997,中央アート出版社,p.211
「それだけは誰も僕から奪えやしない!」 という部分が,まさに 《They Can't Take That Away From Me》 というタイトルになっているわけだ。
彼女との思い出なんていうのは,確かに,他人には誰も奪えないものだろう。ただ,「時」 がそうした思い出を奪っていくことは止められない。細部にわたるまで,昨日のことのように記憶していたことも,何十年もの間に,少しずつ細部がぼやけてしまうことがある。イメージとしては,なんら変わらずにしっかり覚えている・・・と思っているのに,振り返ってみると,周辺に霞がかかったような感じがする。そう気がついた時に,茫然としてしまう。「老い」 とは認めたくない。だから,「時」 のせいだと言い換えただけに過ぎないのかもしれないのだが・・・
上に挙げたアルバムは,Zoot Sims “Zoot Sims And The Gershwin Brothers” (Pablo) で,Zoot Sims(ts), Oscar Peterson(p), Joe Pass(g), George Mraz(b), Grady Tate(ds) といういかにも Pablo らしいメンバーで 1975 年 6 月 6 日に録音されたものだが,もともとのLPには収録されていなかったようで,CDで初めて発表されたボーナス・トラック。
写真は,Lee Tarnner。

《わ が 恋 は こ こ に》
これも Gershwin 兄弟の名曲だが,アルバムによっては,《Our Love Is Here To Stay》 になっていたりする。しかし,《Love Is Here To Stay》 というのが,正しい曲名のようだ。‘our love is here to stay’ と歌詞にはあるから,ま,どっちでもいいか。
ここに挙げたアルバムは,大阪の道頓堀にあったジャズ・クラブ St.James のオーナー・ピアニストだった 田中武久 さんの 2008 年 5 月 8,9 日に録音された最後のアルバム “Too Young” (Jewel) だ。メンバーは,Takehisa Tanaka(p), Yosuke Inoue(b), Masahiko Osaka(ds)。アルバムを聴いていると,あの店内のピアノに向かっていた姿を思い出す。本当に,ピアノを弾くこと,ジャズすることがお好きだったんだろうと偲ばれる。
写真とデザインは Hitoshi Kondo。
2014 年 12 月 28 日にお亡くなりになってしまったが,私は,何度か,お店で生演奏を聴かせてもらったものだ。満員の客で,やっと離れたカウンターに席を見つけたこともあれば,開店間もなくで,ほとんど客もいない中で,まるで私のために弾いてくださったようなこともあった。広くはない店だったので,ソロ・ピアノからクインテットぐらいまでだったように思うが,ソロでもバッキングでも歌伴でも,どんな時でも,もちろん一切手抜きのない,素晴らしいピアノだった。リクエストすれば,即座に応じてもくださった。
アルバムとしては,Elvin Jones との共演盤を含めて,僅か 4 枚残されただけだが,どれも一聴に値するアルバムであることは言うまでもない。
You Tube には,田中武久(p),石田裕久(b),東原力哉(ds) による 《Come Rain Or Come Shine》 (この曲は,上のアルバムでも演奏されているが,まったくテンポも違った演奏だ) などのお店での ライブ の様子がいくつもアップされているので,ご覧になってください。
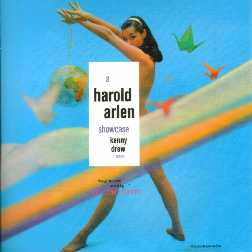
《絶 体 絶 命》
Kenny Drew が ベースの Wilbur Ware と 1957 年に作った作曲家シリーズのアルバムが何枚かあるが,その一枚である “A Harold Arlen Showcase” (Judson 原盤)。数年前,LP TIME からCD化された。
マニア垂涎のお色気ジャケットは,Paul Weller と Paul Bacon によるもの。
《絶体絶命》 なんて言葉,最近はあまり聞かないような気がするが,どんなものか。それに,ネットで検索してみると,「絶対絶命」 って漢字が出てくるところもある。それは,明らかに 「誤字」 でしょう。というか,勘違い。ところが,こういうのが,何年も経つと,ま,いいか,になることがあるから,コトバは難しい。だんだん,元の意味が失われてしまうのだ。
それはともかく,スタンダード・ナンバーの 《絶体絶命》 はというと,原題は,《Between The Devil And The Deep Blue Sea》 という。Ted Koehler の作詞,Harold Arlen の作曲した 1931 年の歌で,コットン・クラブ (Cotton Club) で演じられた “Rhythmania” というショーのために書かれたもの。コットン・クラブといえば,Duke Ellington 楽団が有名だったが,このショーは,Ellington 楽団が辞めたあとに入った Cab Calloway のバンドが演奏した。当初は,あまり流行らなかったようだが,その後,時間をかけてじわじわと有名になったらしい。
きみを嫌わなくちゃいけないのに、どうも愛してるみたいだ
きみは悪魔と深海の狭間に僕を追い込んで
身動きできなくさせてしまったのさ,絶体絶命だね
村尾陸男 著 『ジャズ詩大全 6』,1992,中央アート出版社,p.30-31
この between the devil and the deep blue sea というのは,英熟語で,英和辞典にも,devil を引くとちゃんと出てくる。
be between the ~ and the deep (blue) sea 進退窮まって.
岩崎民平 監修 『現代英和辞典』,1973,研究社
進退窮まる・・・まさに崖っぷち,絶体絶命の場面,といえば,一頃流行った 2 時間ドラマの最後みたいだね。
その崖っぷちのシーン,今では定番過ぎるほどだが,元々は,1961 年に公開された野村芳太郎 監督が映画化した松本晴張 原作の 『ゼロの焦点』 で映像化されたのが最初らしい。原作にも,崖っぷちの場面はあるが,映画とは,場所が違うようだ。

《言 い 出 し か ね て》
《I Can't Get Started》 を 《言い出しかねて》 と訳すと,ほぼ直訳といってもいいが,すごく日本的な情緒を感じさせる名訳だと,かねがね思っている。
現代では,直接的に,「好きだ,愛してる」 と言うのかもしれない。面と向かっては言えないまでも,メールなどで,はっきり伝えるのだろうか。少なくとも,お互いに,はっきり言って欲しい,とは思っているだろう。世の中,昔に比べれば,ずいぶん変わってきたとはいうものの,日本人の習慣としては,はっきり言えないことは残っているようではある。
その反面,あまりにもグイグイと押されると,シンドイと感じてしまうようでもあり,恋愛に関しては,メンドーと感じてしまう人も増えているという。
密かな恋心が極端になると,ストーカーにつながっていく・・・どうも,現代は,ムズカシイ。
淡い恋心を持ちながらいっしょに散歩しながら,どうしても伝えられなくて,そのまま歩くだけで帰ってしまう,あるいは,意を決して,「月が綺麗だねぇ・・・」 というコトバに託してみたり,それで,なんとなく分かり合えた時代は,もう昔々の話なんだろう。
そんな昔と現代の狭間の時代,昭和の終わりごろ,私は結婚したのだが,そんな時代に,私を捉えた一編の漫画がある。高橋留美子さんの名作 『めぞん一刻』 だ。『ビッグコミックスピリッツ』 に,1980 年 11 月号 (創刊号) から 1987 年 4 月 20 日号 (19号) まで連載されていたそうだが,私が知ったのは,1986 年 にテレビ・アニメになってからのことで,結婚した翌年だった。その後,コミック本も全 15 巻揃えたし,1993 年に出版された 『一刻館の思いで 或る愛の物語』 (ワニブックス) という,あの頃流行った 「謎本」 まで買ったものだ。
『めぞん一刻』 については,ご存知の方も多いだろうから,詳しく話すことはないが,一口で言えば,主人公の五代くんと管理人さんの響子さんのラブ・コメディーだ。
その五代くんが管理人さんにプロポーズしようとする時に,
(五代) 「お、おれ・・・響子さんの・・・
響子さんの作ったミソ汁・・・飲みたい」
(響子) 「・・・・・・ ・・・・・・・」
(五代) 「・・・・・・ ・・・・・・・」
(響子) 「・・・はい ・・・・・・・」
(五代) 「・・・・・・ ・・・・・・・」
(響子) 「ちょうど惣一郎さん (いぬ) の朝ごはんに残しといたんです。」
・・・(中略)・・・
(五代) (わすれていた・・・
響子さんは 鈍いんだ。
凝った言い回しはこの女 (ひと) には通用しない。)
高橋留美子 『めぞん一刻 157 話 / 許さん』 (初出:『ビッグ・スピリッツ 1987年3月23日号』),
(1987,小学館,ビッグ コミックス,『めぞん一刻 15 桜の下で』 所収,p.122-124)
この場面は, 『めぞん一刻』 の中でも名 (迷) 場面のひとつだろう。だから,テレビ・アニメ版でも,第 94 回 『やったぜ! 五代くん 決死のプロポーズ!』 (1988.2.17. 放映) で使われている。
もっとも,原作 (158 話 『約束』) にしろ,アニメにせよ,この後に,もっと素晴らしい場面があって,その前振りのようなものといっていいかな。
いずれにしても,はっきりと単刀直入に言いたいけど,なんだか言い出せない・・・言い出しかねて,だけど,遠回しに言いたくなってしまう,そういう微妙な心持ちだ・・・
こういうのは,古いんだろうか。それとも,今は,こういう微妙な言い方なんてのもしないんだろうか。
忘れていた・・・選んだアルバムは,“Introducing Paul Bley” (Debut) で,Charles Mingus と Art Blakey とのトリオ。大物二人にバッキングされた Paul Bley のデビュー盤だ。1953 年 11 月 30 日の録音。
カヴァーは Spilka と右上にサインがある。
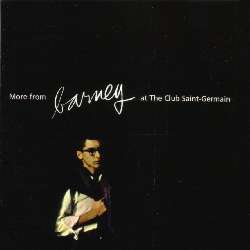
《時 の 過 ぎ 行 く ま ま に》
ハンフリー・ボガート (Humphrey Bogar) とイングリッド・バーグマン (Ingrid Bergman) の名作映画 『カサブランカ (Casablanca)』 でおなじみの 《As Time Goes By》。《時の過ぎ行くままに》 という邦題で知られているようだが,実は,これは,まったくの誤訳。そのタイトルにあやかった沢田研二のヒット曲もあるのだが・・・。誤訳については,ずいぶん前に 『スタンダードの世界』 に書いたので,そちらを見てもらいましょうか。それに,この映画については,何回も触れているから,今回はやめておく。
アルバムは,“More From Barney At The Club Saint-Germain Barney Wilen” (RCA) で,Kenny Dorham(tp), Barney Wilen(ts, ss), Duke Jordan(p), Paul Rovère(b), Daniel Humair(ds) というクインテットで,1959 年 4 月 24, 25 日にパリの ‘The Club Saint-Germain’ でのライブ。《As Time Goes By》 では,Kenny Dorham がテーマからソロ,引き続いて Barney Wilen のテナー,Duke Jordan のピアノ・ソロへと続く。
カヴァー写真については,「×」 印として記載されている。中のブックレットなどの演奏中の写真は,Jean-Pierre Leloir と記載があってのことだから,どうやら調べてもわからなかったのだろう。
『スタンダードの世界』 にも引用したが,ここでも一節を引用しておこう。
そう、これだけは忘れないでいてほしい
キスはやっぱりキスだということ、溜息はただの溜息だということを
どんなに時が経ってもこういう当たり前の事ごとは変わらないのさ
村尾陸男 著 『ジャズ詩大全 1』,1990,中央アート出版,p.39
確かに,愛情表現のキスなんて,ずいぶん昔から変わっていないんだろう。
と思いつつ,ふっと,19 世紀のオーストリアの劇詩人 フランツ・グリルパルツァー (Franz Grillparzer) のコトバを思い出した。彼が 1819 年に発表した 『接吻 (Kus)』 という作品の中の台詞だという。
手の上なら尊敬のキス。
額の上なら友情のキス。
頬の上なら厚情のキス。
唇の上なら愛情のキス。
閉じた目の上なら憧憬のキス。
掌の上なら懇願のキス。
腕と首なら欲望のキス。
さてそのほかは、みな狂気の沙汰。
さて,21 世紀の現代では,どうなんだろう。納得もし,おやっと思うこともあるかもしれない。
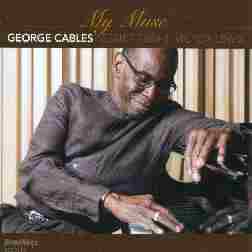
《追 憶》
George Cables の “My Muse” (High Note) が左のアルバム。
Alan Nahigian の写真で,デザインは Keiji Obata and Peter Muller。こういうブラウン系の色調が好きだということもあるが,気にいっているジャケットの一枚だ。
George Cables のオリジナル 4 曲に,ドラムスの Victor Lewis のオリジナル 1 曲の他,6 曲のスタンダードを ベースの Essiet Essiet とのトリオで演奏する。もっとも,最初と最後は,ピアノ・ソロだが・・・。どれも,George Cables の品位を感じさせる好演だ。
トリオで演奏される 《The Way We Were》 という曲は,1973 年のアメリカ映画,『追憶 (The Way We Were)』 の主題歌で,作詞はアラン・バーグマン (Alan Bergman),マリリン・バーグマン (Marilyn Bergman) 夫妻,作曲は,マーヴィン・ハムリッシュ (Marvin Hamlisch)。ロバート・レッドフォード (Robert Redford) と共に主演したバーブラ・ストライサンド (Barbra Streisand) が歌い,アカデミー歌曲賞 (Academy Award for Best Original Song) を得ている。
この映画は,1945 年の第二次世界大戦 終結後のアメリカでの学生運動に深く結びついている。ソ連との冷戦,国内でのマッカーシズム (McCarthyism) に揺れ,朝鮮戦争からベトナム戦争へと続くアメリカ。そうした時代の流れの中で学生たちが平和と自由を求めて運動した時代だった。
泥沼化するベトナム戦争への批判,抵抗といった政治運動の一方で,同様の根を持ちながら,ヒッピーなど文化的な側面でも,古い文化への抵抗・否定する若い人たちの新しい価値観に基づいた文化が現れる。キリスト教的なものとは異なった,インド哲学やイスラム文化への志向,より精神的というかスピリッチュアルなものを求めていく。ジャズの世界でも,イスラム名に改名したり,Coltrane のように,イスラム的,精神的な方向に向かっていった。しかし,音楽面では,反戦歌,プロテスト・ソングといったフォーク・ソングからロックなどが,より受け入れられ,たとえば,1969 年 8 月に開かれた,伝説の 「ウッドストック・コンサート (Woodstock Music and Art Festival)」 がその象徴的な出来事だったといえるかもしれない。
日本でも,朝鮮戦争がらみで沸き,高度経済成長を目指す政治・経済界の一方で,60 年安保などから,学生運動が始まっていく。東大の安田講堂の占拠など大学封鎖があちらこちらであり,それと同じ時期に,工場排水,排煙などによる公害が明らかにされていく。九州や北海道での炭鉱の閉鎖なども相次ぎ,経済界も大きな変換期であった。
その一方で,「東京オリンピック」 や 「日本万国博覧会」 などといった 「お祭り」 も開かれた。「明治百年」 と騒ぎ,「戦後 20 年」 と言い,「もはや戦後ではない」,「人類の進歩と調和」,「明るい未来」 が叫ばれもした。
やがて,日本の学生運動は,1972 年の 「あさま山荘事件」 後,急速に萎えていく。
こうした 1960 年代から 1970 年代という時期に,私は,思春期を過ごした。1962 年に小学校に入学し,1980 年に大学を卒業したのだ。世間,社会,世界・・・そういったことを理解していく時期がそんな激動の時代だったといえる。学生運動に参加するには,まだ子どもであり,学生になった頃には,そんな運動は影をひそめていた。「シラケ世代」 とも言われた。それは,しぼんでしまった 「学生運動」 に対してでもあり,また,「お祭り騒ぎ」 に対しても,乗り切れない部分があったからだろうか。
あの,なんともいえない時代が,ある意味では,私の 「原点」 なんだろうと今さらながらに思う。「学生運動」,「万博」,「公害」,「月面着陸」,「世紀末」,「UFO」,「邪馬台国」・・・そうしたいろんな流行を楽しみながらも,自分の内面のどこかで,「胡散臭さ」 も感じてしまっていたのは,今も変わっていないような気がする。
(2019. 4.19.)